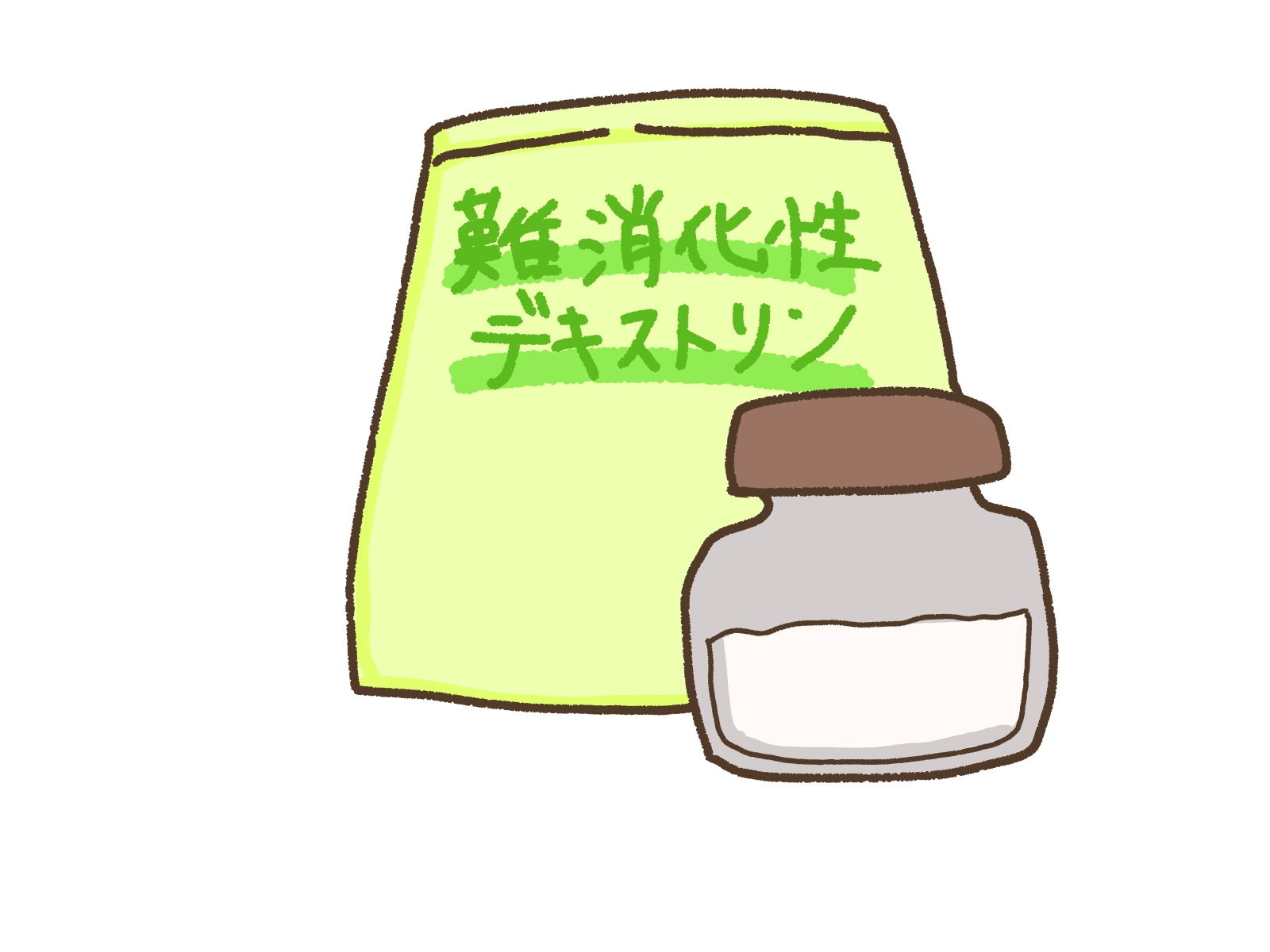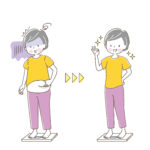難消化性デキストリンとは、水溶性の食物繊維の一種で、とうもろこし由来のデンプンから作られています。
体内でほとんど吸収されずに小腸を通過し、大腸に到達。その一部は腸内細菌に利用され、残りは排出されます。
糖質や脂質の吸収スピードに関与するほか、腸内環境や脂肪に関するデータもあり、健康を意識した食生活をサポートする成分として注目されています。
健康サポートに期待される6つの働き

難消化性デキストリンに関して報告されている、主な6つの働きを見てみましょう。
食後血糖値の上昇を穏やかにする
炭水化物と一緒に摂取することで、糖の吸収がゆるやかになり、食後血糖値の上昇を抑える作用が期待されています。
脂質の吸収を穏やかにする
脂っこい食事と一緒に摂ることで、中性脂肪の上昇をゆるやかにする可能性があるとされます。
腸内環境を整える
水溶性食物繊維として腸内の善玉菌のエサになり、腸内環境のバランスを整える手助けをします。
お通じの乱れが気になる方にも注目されています。
中性脂肪やコレステロールへの働き
1日3回、1食あたり約10gを目安に継続摂取することで、中性脂肪やコレステロール値が低下したという報告もあります。
内臓脂肪に関するデータも
同様の摂取条件で、内臓脂肪の面積が減少したというデータもあり、体型維持にも期待されています。
ミネラル吸収をサポート
カルシウムやマグネシウムなどのミネラルの吸収を助けるという報告もあり、栄養バランスを意識する方にも嬉しいポイントです。
どんな形で使われている?
難消化性デキストリンは、健康サポートを目的とした食品や飲料に幅広く使われています。
- 特定保健用食品(トクホ)のお茶やジュース
- サプリメント
- 粉末タイプ(料理や飲み物に混ぜられる)
自身の生活スタイルに合わせて、無理なく取り入れられるのが特徴です。
無理なく取り入れるコツ
取り入れる際は「一度にたくさん」よりも「毎日の習慣に少量ずつ」がポイントです。
過剰摂取はお腹がゆるくなる場合もあるため、パッケージの目安量を守りましょう。
なお、日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、食物繊維の1日あたりの摂取量の目安は、女性18g以上、男性1日21g以上(ともに18~64歳の場合)と定められており、そのうち食物繊維不足を補うための難消化性デキストリンの摂取量は1日あたり5gが適量とされています。
健康をサポートする成分として、バランスの良い食生活の中に無理なく組み込むことが大切です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、また次回もお楽しみに♪